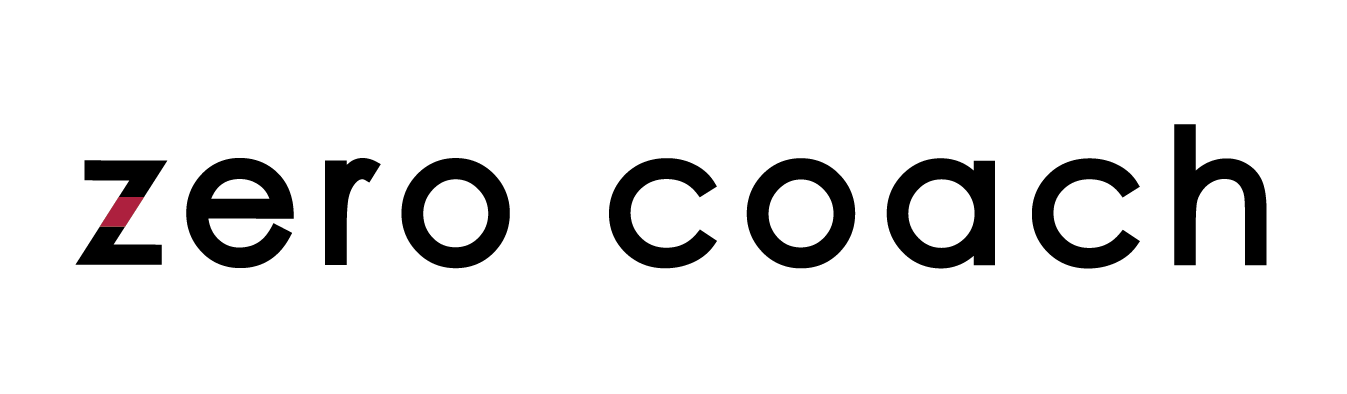10代、とりわけ小中学年代におけるサッカー人口は減少しつづけている。傾向という曖昧なものでなく確実に減少しているようだ。
この記事では小中学年代をメインに、サッカーの実施率と登録数のデータを参考に、サッカー人口の減少について考える。
このサッカー人口の減少は、目を背けてはならない非常に重要な課題である。
なぜ重要か?

このままではサッカー人口は確実に減少していく。しかも激減する可能性があると考えている。
小中学年代のサッカー人口の減少を検証し、すぐさま課題への対策を講じなければ、現状を維持することはおろか確実にその数は減っていく。
私が考える減少を引き起こす二つの要因を紹介したい。この二つの要因は、地域の指導現場を視察して得た、主観的な見解である。
- 入り口の減少
- 結果主義
入り口の減少と結果主義

二つの要因はサッカー人口の減少に、少なからず影響を与えていると考える。くり返すがその対象は小中学年代である。
近い将来、この二つの要因はサッカー人口の横ばい状態を維持する、高校、大学年代へと推移していくはずだ。
入り口の減少
「サッカーへの入り口が無い」指導現場を視察すると、いつもこの言葉が浮かんでくる。
サッカーの練習では、幼い子が難解な反復を要求され、自分の順番がくるまで長い時間待たされる。そして9歳10歳になるとサッカー用語が飛び交い、戦術を基盤にサッカーのあり方が幼い年代から形づくられていく。またこの頃になると子どもの評価は、技術レベルに応じ明確に区分される傾向にあるようだ。
専門的指導は初心者への敷居を高くし、サッカーへの興味の壁をつくってしまう。つまり高度化した専門的指導がサッカーへの入り口を無くす要因になっているのだ。
結果主義

加速していく結果主義。
大会やリーグ戦など、勝敗の結果はチームの評判に大きな影響を与えるようになった。じっさいにこの評判はチーム運営に大きな影響を与えている。
そして現在、この評判を良い状態に保つために、試合結果が何にも増して分かりやすい指標となっている。だから結果主義へと傾倒する指導がなくならない訳にも頷く。
またこの結果主義は、子どもの能力評価へも強い影響がある。
チーム運営には一定の会員数を担保することが重要で、その鍵は試合結果であることはすでに述べた。
この試合結果を得るために、コーチはできる子とそうでない子を能力評価により分類するようになる。つまり、勝つための分類である。その分類には「将来性」や「育成」といった概念は存在しないことも多いのではないだろうか。
実施率
10代のサッカー人口として、笹川スポーツ財団に興味深いデータが掲載されているので紹介したい。
それによると小中高年代のサッカー人口は2013年〜2015年を境に減少。大学年代は横ばい状態だそうだ。

このサイトには男女比、年代別など様々なデータが示されているので、興味のある人はぜひ目を通してもらいたい。
登録数
日本サッカー協会が示すサッカー登録数データによると、小中学年代の登録数は2013年〜2014年をピークに減少しつづけている。
ちなみに、2000年からスタートしたシニア年代の登録数の伸び率は、2023年時点で900%と驚異的な伸びを見せている。
これら実施率と登録数について、おおよその減少時期(2013年から2015年)の一致に共通点があるかは不明である。
不具合
ライセンス制度は整えられ、指導者の登録数は年々増加している。しかしその反面、小中学年代でサッカー人口の低下が見られる。そしてサッカー人口は減っているにも関わらずチーム数は増加傾向(新規クラブの増加)にあると最近耳にした。
何かおかしなことが起こってはないだろうか?
減りつづけるサッカー人口の理由を、きちんと説明するためのリサーチはまだ完全ではない。しかし、これら身の回りで起こるる不具合を感じているのは、決して私だけではないだろう。これらの不具合を考察することは、入り口の減少や結果主義を改善し、サッカー人口の減少を食い止めるヒントへ繋がっていくと考えている。